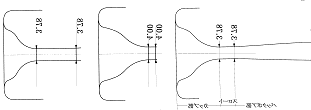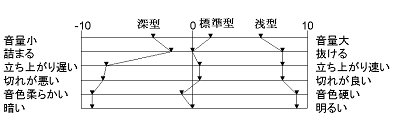| 楽器創造館 第二期スタート記念パーテイ リポート |
|---|
以下に当日の資料を掲載いたします |
|---|
| 楽器創造館の活動についての 一考察 | |
|---|---|
| 館長 永井 洋平 |
| 楽器の科学的研究の成果が世の中に貢献できる場合を大きく分ければ下記のようになろう。楽器創造館の活動は、このような成果の実現に向けた直接活動、および成果へ向けての情報発信、研究者支援などの間接活動である。 | |
| 1.既存楽器の (1)機能の改良を果たした場合 (2)製作コストの低減を果たした場合 |
例: ピアノ低音部の音色改良、電子楽器の音色改良・操作性改良サキソホンの ウルフトーン減少、ヴィブラフォンの音程感改良 例: 電子楽器用半導体の集積度向上、電子音源ピアノ金管楽器テーパ管成型、 FRPスーザホンピアノ用プラスチックアクション、自動調律リード |
| 2.既存楽器に新機能を付加した場合 | 例: 自動演奏ピアノ、消音ピアノ、減音管楽器、フルートのEメカ電子楽器の自動伴奏・自動作曲、映像発生電子楽器 |
| 3.新しい楽器を開発した場合 | 例: アドルフ・サックスのサキソホン、エレキギターヤマハミブリ、ラジオドラム、 電子ドラム、電子バイオリン |
| 4.楽器についての間違い信仰(神話)を是正し、業界を納得できる方向に動かした場合 | 例: 高価イタリア・バイオリン神話 スタインウェイ・ピアノ神話 <既にヤマハによる成果が見られるもの> バック・トランペット神話、クランポン・クラリネット神話 セルマー・サキソホン神話、アレグザンダー・ホルン神話 |
◆
| 今後の課題例をひとつ考えてみましょう : 高価イタリア・バイオリンは本当に価値があるのか? |
||
| < ズバリ直接論拠 > | < 間接論拠 > | |
| (A)本当に価値があるとする説 | 全ての一流奏者が使っている | ・古い木がよい ・昔の塗料がよい |
| 現実の売買相場が高価である | ||
| (B)神話に過ぎないとする説 | ナシ | ・300年前の工学的技術レベルは低い ・大半が後世の修理で古くない木の板で接ぎだらけ ・入手以後しばらくは鳴らなかったという奏者の告白が多い ・世界一の演奏者の評価力にも大いに疑問あり ・科学的な評価テストは行われたことは一度もない ・先生の言うことを信ずるタテ世界 ・高価な楽器が悪いはずがないと思って一生懸命弾く ・良くない音が出たら奏者の責任と思って一生懸命弾く |
| (B)の状況証拠(間接論拠)に自信あり、 世界一奏者の賛同を得て客観性ある科学的なテストを行えば長年の疑問が解決する。 |
| 想定する結論は:骨董品価値、発露する音質価値が別々に評価されて価格が決められるべきである。 高級イタリア製以上の良い 性能の楽器が沢山ある。 |
■ 楽器づくりと木材接着ー接着の寿命 ■
| 岩田 立男 |
|---|
| 長期に伝統ある楽器(ピアノなど)・家具・ドアなどの構造材として使用されている硬木材集成接着品の接着品質は重要課題となっているが、その接着剤の耐久性選定基準が不明確な現実がある。 本研究では、楽器など構造部材として実績のある密度0.6g/cm3以上の広葉樹材を使用した高品質な集成材について、木材用接着剤を12種類選定し、構造部材が使用される環境を予測した促進要因による環境試験を実施して、人工的に促進した小型テスト片試験の接着強さとの関係を明らかにすることより、小型テスト片で代替評価し、その接着剤の耐久性選定基準を明確にすることを検討した。 硬木材集成接着品の試験方法として屋内製品を対象とすることから、湿度・温度を耐久促進因子としてブナ材3plyブロック品(厚さ30mm、幅80mm、長さ530mm)を用い実環境を予測した耐湿耐乾試験、冷熱試験および屋外暴露試験を実施した。 小型テスト片の試験方法としてカバ材25mmラップ品(厚さ10mm、幅25mm、長さ50mm)を用い耐水性および耐熱性せん断接着強さを測定した。 接着剤としてはレゾルシノール樹脂接着剤、水性高分子―高分子イソシアネート系樹脂接着剤、酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤、エポキシ樹脂接着剤など木材用に使用されている接着剤を選定した。 結果を以下のようにまとめることができる。 (1)集成材の耐湿耐乾試験、冷熱試験および屋外暴露試験においては、接着はく離が発生した。 (2)集成材の屋外暴露試験後の接着はく離率と小型テスト片の60℃耐水接着強さは、相関性を示した。 (3)集成材の冷熱試験後の接着はく離率と小型テスト片の100℃耐熱接着強さとは、強い相関性を示した。 また、集成材の屋外暴露試験後の接着はく離率は、小型テスト片の100℃耐熱接着強さとも相関性を示した。 集成材の接着耐久性へ及ぼす接着剤樹脂の性質による影響をより詳細にとらえるため、接着剤の熱的性質および透湿性との関係を検討し、「接着剤のガラス転移温度Tgおよび透湿率は、集成材の接着耐久性における接着剤選定の重要な要因である」と推定できた。 本研究により、木材接着品の中で耐久性が最も不明確であった硬木材集成接着品用の接着剤選定基準が明確となり、“木材”の有効利用&“長寿命化”の循環型社会形成への貢献となった。 なお、本研究で定めた接着剤の耐熱性および耐水性基準を利用し、合板並みの性能を示す新規木質ボードの開発にも適用できた。 以上 |
|---|
◆ 金管楽器の吹きやすさと鳴らしやすさ ◆
| 楽器創造館 http://gakkisozo.gotohp.com/ 村上和男 |
|---|
1. 金管楽器の吹きやすさ、鳴らしやすさとは 吹きやすさは奏法入力の効率、鳴らしやすさは管体の音響特性制御の難易度 奏法と音響管の特性の相乗効果として、吹奏感と音色の良さが評価される
2. 吹奏感と音色を決める要因 金管楽器、特にトランペットについて、吹奏系を想定して、奏者にとって 吹きやすさと、鳴らしやすさに関する要因は次の吹奏要件に分類できるであろう。 (1) 管楽器としての基本要件 (2) 吹き易い為の要件 (3) 大きい音でよく鳴る為の要件 (4) 高度な奏法を満たす要件 マウスピースのカップ部の形状 浅型 深型 標準型
マウスピースの吹奏感評価
特徴を挙げれば,標準に対して, カップの深いのは暗く柔らかい音色で, 詰まり気味で鳴りにくく,レスポンスも立ち上がりが遅く,切れも悪い。 カップの浅いのは明るく硬い音色で, 音量が大きく良く抜ける。レスポンスは立ち上がりが速く,切れも良い。 |
|---|
■ 音楽DVD制作の楽しみ ■
| 上神谷 俊喜 |
|---|
| 映画やテレビドラマはもちろんのこと、映像に関わるあらゆる作品には音楽が付いているのは最早あたりまえのことである。また、たとえ無音の部分があったとしても、それはその部分が次の音楽挿入部を引き立てる意味さえ持っている場合もありそうだ。 このように、情報量的には映像よりは遥かに少ない音声や音楽が、映像にもまして我々の心を捉え生活の一部にさえなっているのは何故なのか・・? の追求はまた別のところでしてみたいところですが、ここではその昔、8ミリフィルム時代の無音声だった頃を振り返ってみます。(のちに、マグネチックのモノラルトラック付きのフィルムや対応機器が発売されるわけですが。) その無音時代の終盤に入った頃、「パルスシンク」と称して8ミリ映写機と外部のオープンリールのテレコを連動させてくれる機材が存在した時期があります。テープヘッドが主要パーツのこのアダプターをテープデッキの録再ヘッドの脇に固定し、映写機側で発生させたパルスをDINコード(ケーブル)で受け取り、ステレオテープの片チャンネルに記録。映写時、モノラルBGMはスピーカーへ、もう片chの同期用のパルスは映写機駆動系のパワートランジスタなどをドライブしていたようです。 ナレーション等とのリップシンクにはなかなか大変でしたが、BGMのフレーズ合わせ程度なら問題なく使えました。そして何よりも重宝なことには、テープデッキを再生させるだけで映写機も連動してスタートしてくれたことがなんとも有り難かったこと・・・。 無音だったフィルム映写が、初めてBGMの入った形でスクリーンに写し出された時は、とにかくその映像だけだった時に比べて数倍も輝いて見え、大げさに云えば宇宙から新しい生命でも注ぎこまれたのでは、というくらいの感動だったことを思い出します。 《今回の投射ビデオ》 ① 楽器フェアeSax (HDV→HD-WMV→MPEG2) ミュージック・シーン撮影の面白さは、演奏曲のテンポやフレーズに合わせたカメラワークにあり。 パン、チルトやズームは勿論だが、三脚やドーリーから離れてカメラ移動する時の手ぶれ感にもありそうな気がする。その手ぶれがその時のビートにうまく乗っていた時などは、まさしく自己満足の世界に陥るには最高の時だ。ワンカメの帝王を目指すべく撮影後の編集も楽しいが、一つの曲の中で別アングル・別フレーズの絵を、あたかも2カメで撮っているようなトランジションが当てはまったときには、うまく誤魔化せたというスリル感がまたなんともいえない。そしてまた、必要とあらばコード進行上問題のない範囲なら、画面構成上、小節の一つや二つ飛ばして繋いだりすることも、音声トラック/クロスフェード遊びの一つだ。 ② ヤマハグランドピアノ・XPプロ (同上) ヤマハの製品(XPプロ)での、動画とMIDI連動再生演奏のデモンストレション・シーンを撮影した。 ③ DVD-MIDI録画 (DV→WMV→MPEG2) 生演奏中のアップライトピアノから出力されるMIDI信号を、JOJ社のフレームレコダ-を使いDVカメラの映像エリアにコーデックしたビデオ。ノンリニア編集時にタイムライン上のトラック間で小細工をし、対ピアノとの発音タイミングを調整している。 今回の映像は、変更前の映像再生をしながらMIDI音源をドライブし、曲の進行中に、その内蔵ピアノ音源をフレーズ単位でいくつか切り替えていきながらダビングして仕上がったもの。 ④ エーゲ海クルーズ (HDV→DV→MPEG2) 撮ってきた映像に音楽をあてはめるには、選曲も一つの楽しみだが、今回はまず先に曲ありき・・・。 いずれにしても、こういった紀行ものにBGMやスクロール文字を入れればオーソドックスな一つのタイトルに仕上がってしまうわけだが、この度は文字まで手が回らなかった分、曲のフレーズとカットの繋ぎめをシツコイくらい調整を重ねた。 以上 |
|---|
| NHK静岡「マイビデオ」 平成19年度 最優秀賞受賞報告 増井 武 |
 |
|---|---|
| 受賞作品はこちら(9MB) NHK文化センター、中日文化センター等、ビデオ教室で研鑚。 リニア編集機に始まって、現在はVAIO/PremiereProをペースにハイビジョン・ノンリニア編集に取組んでいる。 投稿、創作ビデオ等年間を通じ平均的に制作活動をしている。 また、年に2~3作ほど制作依頼等を請けたりしている。 AVCHDコーデック出現に伴い、DVカメラの記録メディアがHDD,DVD,メモリカード等と多元化してきている。 DVテープの先行きは、はたしてどうなるか。 |
TOPページへ この頁トップへ