楽器会社に永らく勤めていた期間に、「私も出来ればこの人のような社会人生活を送りたいものだ」と思える人に出会ったことはあまり多くはない。特に楽器業界で研究的な業務に携わる人の中ではその数も少ないこともあってめったにお目にかかれなかった。しかしながら、ひとりだけお手本のように思えた人がいる。その人の名は、ここにご紹介させていただくダニエル・マーチン(Daniel William Martin)である。初対面は1971年のブダペストのICA(国際音響学会)で私がパリ大学の音響研究室に滞在中に行ったフルート吹奏に関するテーマの発表をしたときであった。セッションの終了後に私に話しかけてくれて的確な感想をコメントしていただき大いに感激した。
当時のマーチン氏はアメリカの大手楽器会社のボールドウィン社(Baldwin Piano & Organ Co. ltd)の技術部長であり実に上品で優しく心の広いおじさんという感じのアメリカ人だった。氏の人生全体における華々しい経歴はとても私の真似のできる範囲にはないが、彼は同じ楽器研究の分野での大先輩でもある。私はマーチン氏の名はトランペットの振動現象を研究した歴史的に有名な論文で覚えがあったのでそのような方とお付き合いさせていただくことは個人的にも自分の会社のためにもきっとプラスになるだろうと思って、その初対面以降も出会うたびに礼を失することがないように努めるようにした。
|
マーチン氏の略歴を紹介すると、1939年という早い時期にイリノイ大学で博士論文のテーマとして「トランペットの演奏家の唇の振動と金管楽器族の放射指向性の研究」を選びこれが本格的な管楽器の科学的研究の先駆けとなった。1940年からRCAに入社し勤務中に咽喉装着用マイクロホンを彼の特許第一号として取得して以来、計26件の特許を取得している。1949年にボールドウィンに入社し、1983年に退社するまでに主としてピアノ音の音質改良、電子オルガンの音色の分析・改良、室内音響の研究を行った。在職中に彼の代表的な著書”Providing for Sounds of Worship”(崇高なる音の発現)を出版した。ボールドウィン退職後は音響技術コンサルタントとして独立しこの分野で広く知られた活動を行っていた。学会面での活動としては1951年以降アメリカ音響学会誌(JASA)の特許解説を担当し約4000件の特許について学会誌用に要約記事を作成した。1984年からの2年間はアメリカ音響学会会長に就任しその後1985年からアメリカ音響学会誌の編集長を務めた。その他にもオーディオ技術教会(Audio Engineering Society)の会長のポストに2年間就くなど同協会の発展にも寄与した。 趣味としての楽器演奏はトランペット、また美声を活かして歌うことが趣味で音響学会メンバーからピックアップされたコーラスカルテットの一人として懇親会などで歌うことが多かった。 |
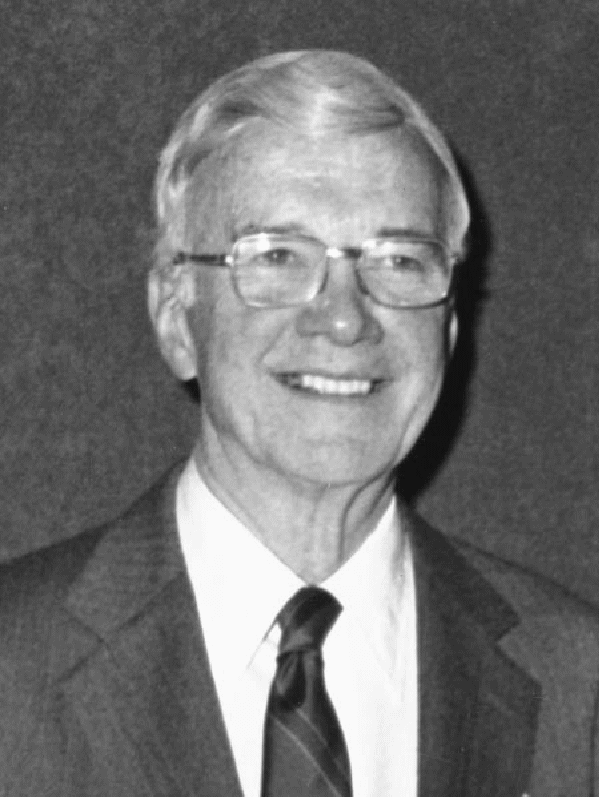 |
|---|
私にはマーチン氏にいろいろとお世話になった思い出がある。オースチンで開催されたアメリカ音響学会に参加した際、マーチン氏は私を音楽研究分科会の委員会に連れて行きゲストとして紹介してくれた。おかげで委員会の進め方などが参考になったし、その時に初めてジョン・バッカスやビル・ストロングなどアメリカの楽器分野で活躍するメンバーとも会うことが出来た。
あるときはシンシナッティ市にあるボールドウィン社の本社と工場を訪問させてくれてアメリカの楽器会社の実情を見せてくれたことがあった。その折には彼自身が担当する研究開発部門を健全に育てるためには会社経営陣と良い関係を保つ必要がありそのために少なからぬ努力をしていることを話してくれて、それを私のその後の会社生活に大いに参考にさせていただいた。その日は彼の自宅にも招待されて奥様にもお会いした。
熱心なキリスト教徒であるマーチン夫妻はともに地元の教会の要職にもあった。毎年クリスマスの季節には子供や孫たちのことも含めた家族の一年間の詳しいニュースが記されているクリスマスカードが毎年届くのが楽しみであった。
私が尊敬の心で接してきたダニエル・マーチン氏が81歳で亡くなられたとの連絡を1999年にマーサ・マーチン夫人からいただき、それが最後のマーチン家からの便りとなってしまった。お墓参りをしてその後のことを報告したいと思う人が外国にも何人か居るがマーチン氏ももちろんその一人である。